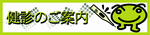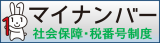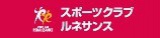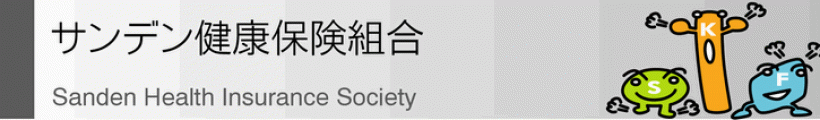
サンデン健康保険組合
Sanden Health Insurance Society
よくある質問とその答え
◆資格確認書について
Q2.住所が変わりました。健保組合に届出は必要ですか。
A2.令和 5 年 12 月 8 日施行の省令改正により、健康保険組合は加入者の住民票住所の把握が必須となりました。住所変更された時は「住所変更届」をご提出ください。
資格確認書に記入した住所は、ご自身で訂正してください。
例)修正ペンを使用しての訂正、二本線をひいての訂正等
A2.令和 5 年 12 月 8 日施行の省令改正により、健康保険組合は加入者の住民票住所の把握が必須となりました。住所変更された時は「住所変更届」をご提出ください。
資格確認書に記入した住所は、ご自身で訂正してください。
例)修正ペンを使用しての訂正、二本線をひいての訂正等
Q3.退職後、今まで持っていた資格確認書はどうすればよいのですか。
A3.退職後すみやかに、ご家族の資格確認書も含め、会社の担当窓口までご返却ください。
※限度額適用認定証、高齢受給者証が交付されておりましたら、併せてご返却ください。
退職日の翌日が健康保険の資格喪失日となります。翌日から資格確認書を使って医療機関を受診しないでください。
退職日の翌日以降に資格確認書を使うと、医療費の窓口負担以外(健保組合負担分)を後日お支払いいただくことになります。
A3.退職後すみやかに、ご家族の資格確認書も含め、会社の担当窓口までご返却ください。
※限度額適用認定証、高齢受給者証が交付されておりましたら、併せてご返却ください。
退職日の翌日が健康保険の資格喪失日となります。翌日から資格確認書を使って医療機関を受診しないでください。
退職日の翌日以降に資格確認書を使うと、医療費の窓口負担以外(健保組合負担分)を後日お支払いいただくことになります。
Q4.資格確認書の裏面の臓器提供意思表示欄は必ず記入する必要がありますか。
A4.意思表示欄への記入は任意です。ご家族とよく話し合いをして判断した上で記入してください。
A4.意思表示欄への記入は任意です。ご家族とよく話し合いをして判断した上で記入してください。
Q5.資格確認書の裏面の臓器提供意思表示欄に記入後、変更したい場合はどうすればよいですか。
A5.既に記入した意思に二重線を引くなどした上で新たな意思を表示してください。
A5.既に記入した意思に二重線を引くなどした上で新たな意思を表示してください。
◆被扶養者について
Q1.妻が仕事を辞め雇用保険(失業給付)を受給予定ですが、受給中も被扶養者でいられますか。
A1.失業給付を受けることの目的は、早く適職を得て再就職をすることにあります。この期間中の状態は一時的なものであり、継続的に被保険者(本人)により生計が維持されているとはみなされませんので、受給期間中は被扶養者になることはできません。
※受給期間中は国民健康保険に加入します。
※ただし、基本手当日額が3,611円未満(60歳以上の方は5,000円未満)の場合は、受給中
も扶養のままでいられます。
A1.失業給付を受けることの目的は、早く適職を得て再就職をすることにあります。この期間中の状態は一時的なものであり、継続的に被保険者(本人)により生計が維持されているとはみなされませんので、受給期間中は被扶養者になることはできません。
※受給期間中は国民健康保険に加入します。
※ただし、基本手当日額が3,611円未満(60歳以上の方は5,000円未満)の場合は、受給中
も扶養のままでいられます。
Q2.妻が就職したので扶養から外します。保険料は安くなりますか。
A2.被扶養者の分の保険料はいただいておりませんので、被扶養者の人数が増減しても保険料は変わりません。ただし、被扶養者の介護保険料を頂いていた場合、保険料が変わります。
介護保険についてQ3を参照
A2.被扶養者の分の保険料はいただいておりませんので、被扶養者の人数が増減しても保険料は変わりません。ただし、被扶養者の介護保険料を頂いていた場合、保険料が変わります。
介護保険についてQ3を参照
Q3.夫婦共働きです。1番目の子を夫、2番目の子を妻の扶養にできますか。
A3.行政通達により、子が何人いても、夫婦どちらか年間収入の多い方の扶養にしなければなりません。
A3.行政通達により、子が何人いても、夫婦どちらか年間収入の多い方の扶養にしなければなりません。
Q4.別居している義父母を扶養にすることができますか。
A3.配偶者の父母を扶養にするには、主としてあなたが生計を維持していることと同居していることが条件です。別居している場合は、扶養にすることはできません。
A3.配偶者の父母を扶養にするには、主としてあなたが生計を維持していることと同居していることが条件です。別居している場合は、扶養にすることはできません。
◆保険給付について
Q1.高額な医療費を支払ったのですが、高額療養費の申請は必要ですか。
A1.申請は必要ありません。病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書(レセプト)」に基づき支給決定をします。高額療養費の対象となった方には、診療月の3ヵ月後、会社を通して自動的に給与と一緒にして払い戻されます。その際、健康保険組合から個人宛てに「支給決定通知書」を送付します。
A1.申請は必要ありません。病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書(レセプト)」に基づき支給決定をします。高額療養費の対象となった方には、診療月の3ヵ月後、会社を通して自動的に給与と一緒にして払い戻されます。その際、健康保険組合から個人宛てに「支給決定通知書」を送付します。
Q2.子供の歯の矯正に50万円かかりました。高額療養費に該当しますか。
A2.歯列矯正は、健康保険の適用対象外です。
医療費控除の確定申告をしてください。
A2.歯列矯正は、健康保険の適用対象外です。
医療費控除の確定申告をしてください。
◆介護保険について
Q1.介護保険は強制加入ですか。介護サービスを受けるつもりが無ければ、加入しなくても良いですか。
A1.介護保険は、介護の負担を社会全体で支えあう社会保険制度です。従って、本人の希望やサービスを利用するしないに関わらず、原則として40歳以上の全ての人が加入します。ただし、次の条件に該当する人は、被保険者(本人)としない特例が設けられています。
・国内に住所がない人
・短期滞在の外国人
・身体障害者養護施設などに入所している人
A1.介護保険は、介護の負担を社会全体で支えあう社会保険制度です。従って、本人の希望やサービスを利用するしないに関わらず、原則として40歳以上の全ての人が加入します。ただし、次の条件に該当する人は、被保険者(本人)としない特例が設けられています。
・国内に住所がない人
・短期滞在の外国人
・身体障害者養護施設などに入所している人
Q2.介護保険料は具体的にいつから負担することになりますか。
A2.満40歳になると第2号被保険者となり、その資格を取得する日は誕生日の前日と法律で定められています。介護保険料は資格を取得した月の分から納めることになりますが、保険料は後払いのため、実際に給与控除が始まるのは資格取得月の翌月になります。
A2.満40歳になると第2号被保険者となり、その資格を取得する日は誕生日の前日と法律で定められています。介護保険料は資格を取得した月の分から納めることになりますが、保険料は後払いのため、実際に給与控除が始まるのは資格取得月の翌月になります。
Q3.被扶養者の保険料も支払うのでしょうか。
A3.令和2年3月から、健保組合に加入している40歳〜65歳未満の家族(被扶養者)の介護保険料を徴収するよう規約を変更しました。
従って、40歳未満もしくは65歳以上の被保険者の方で、40歳〜65歳未満の家族(被扶養者)がいる方は保険料を納めていただきます。被扶養者の人数による負担の差額はありません。
なお、65歳以上の被保険者及び被扶養者の方の保険料は、それぞれ居住する市町村に納める(年金受給者は、原則年金から自動徴収)ことになります。
A3.令和2年3月から、健保組合に加入している40歳〜65歳未満の家族(被扶養者)の介護保険料を徴収するよう規約を変更しました。
従って、40歳未満もしくは65歳以上の被保険者の方で、40歳〜65歳未満の家族(被扶養者)がいる方は保険料を納めていただきます。被扶養者の人数による負担の差額はありません。
なお、65歳以上の被保険者及び被扶養者の方の保険料は、それぞれ居住する市町村に納める(年金受給者は、原則年金から自動徴収)ことになります。
.